脱水症は何日で治る?症状や対処法から熱中症との違いまで解説
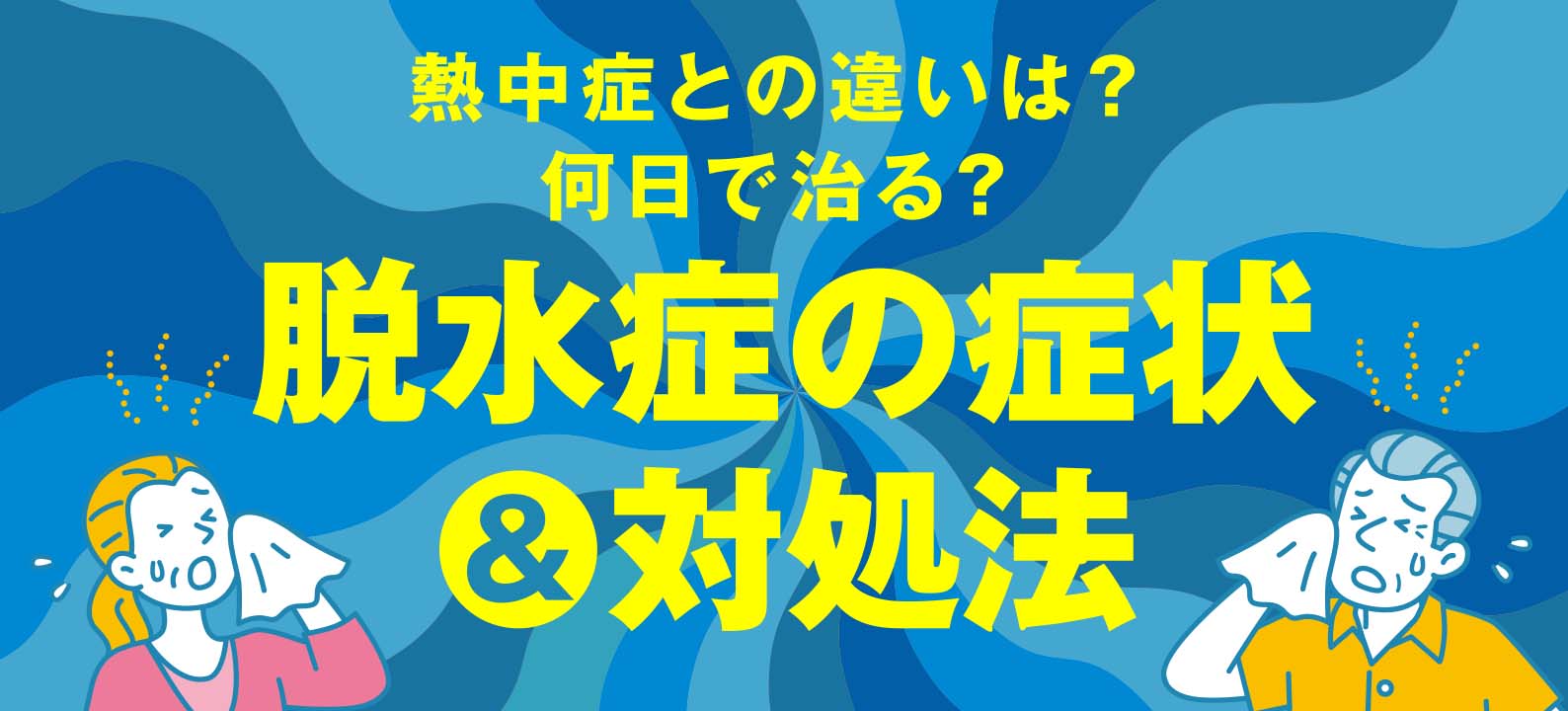
脱水症は、体内の水分と電解質が不足することで引き起こされる症状です。本記事では、脱水症の症状や原因、熱中症との違い、適切な対処法について解説します。脱水症について正しく理解し、早期発見・予防の意識を高め、自信を持ってアセスメントおよび対処ができるようになりましょう。
目次
脱水症とは
脱水症とは、体内の水分とナトリウム(Na)やカリウム(K)などの電解質のバランスが崩れ、必要な体液が不足した状態を指します。私たちは日常的に汗や尿、呼吸を通じて水分を失っていますが、水分補給が十分でなかったり、発熱や下痢などで急激に体内の水分が失われたりすると脱水が進行します。
脱水症の症状
脱水症になると、血液の循環が滞り、血圧が低下します。また、全身への栄養供給が十分に行われず、老廃物の排出機能も低下してしまいます。主な症状は、口の渇きや倦怠感、食欲減退などです。また、筋肉や骨に必要な電解質が不足すると、足がつったり、しびれを感じたりすることもあります。
また、脱水症の症状の重さは、体内の水分がどの程度失われたかによって異なります。
- 軽度(体重減少率1~2%)の脱水:
喉の渇きを強く感じるようになり、尿の回数や量が減少します。また、発熱や軽い下痢、嘔吐など、消化器官や全身に症状が現れる場合もあります。 - 中等度(体重減少率3~9%)の脱水:
倦怠感が強まり、めまいや頭痛が現れます。血圧や臓器の血流が低下するなど、全身に影響が生じます。 - 重度(体重減少率10%以上)の脱水:
生命に関わる危険な状態です。心臓や腎臓の機能が低下し、血流が著しく減少することでショック状態に陥る可能性があります。意識がもうろうとしたり、極端な低血圧により臓器不全を引き起こしたりすることもあり、迅速な対応が必要です。最悪の場合、死に至ることもあるため、重度の脱水に至る前に対処しましょう。
脱水症の原因
身体から水分が失われる主な要因は以下のとおりです。
| 原因 | 説明 |
| 朝食を抜く | 睡眠中に呼気や発汗で水分が失われているため、朝食を抜くと補水の機会を逃し、脱水のリスクが高まる |
| 寝すぎ | 長時間にわたって水分補給をしない状態が続くことで、体内の水分が不足し、脱水を招く可能性がある。就寝中も汗をかいているため、睡眠時間が長くなるほど脱水傾向が強まる点にも注意が必要 |
| ストレス | 緊張が続くと交感神経が活発になり、心拍数や体温が上昇することで水分消費が増え、脱水状態になりやすい |
| 高温の室内環境 | 風通しが悪く、エアコンを使わない室内では発汗が促され、水分不足になりやすい |
| 二日酔い | アルコールの利尿作用により体液が過剰に排出されるため、翌朝に脱水症状を引き起こしやすい |
| 発熱 | 体温上昇により発汗が増え、水分が失われることで脱水のリスクが高まる |
| 下痢や嘔吐 | 感染症や食あたり、体調不良などによる下痢や嘔吐で、体内の水分や電解質が急速に失われる |
| 食べ過ぎ | 消化のために胃腸へ血液が集中することで全身の血流が低下し、体温調整が乱れ、脱水を引き起こすことがある |
脱水症と熱中症の違い
脱水症が進行すると、体温調節が難しくなり、熱中症に移行するリスクが高まります。脱水症と熱中症は混同されやすいですが、熱中症は、高温環境の中で体温調節機能が適切に働かなくなることで発生する症状の総称です。体内の水分・電解質のバランスが崩れ、体温が異常に上昇することで、めまいや吐き気、強い倦怠感が生じることがあります。重症例では、けいれんや意識障害を伴い、適切な処置が行われなければ生命に危険を及ぼす可能性があります。そのため、早期発見と迅速な対応が不可欠です。
脱水の種類
脱水は、原因や体液の失われ方によって「高張性脱水」「等張性脱水」「低張性脱水」の3つのタイプに分けられます。それぞれの特徴と主な原因は次のとおりです。
高張性脱水
高張性脱水は、血液中のナトリウム濃度が高くなり、細胞内から細胞外へ水分が移動し、細胞内液が減少した状態のことをいいます。大量に汗をかいたにもかかわらず十分な水分補給ができていない場合に発生しやすく、循環血液量は保たれますが、強い喉の渇きを感じるのが特徴です。
また、脳血管障害や脳腫瘍、頭部外傷などによって口渇中枢の機能障害がある場合、自覚しないまま脱水が進行することがあるため、特に注意が必要です。
等張性脱水
等張性脱水は、水分と電解質がほぼ同じ割合で失われる血漿浸透圧の変化を伴わない脱水で、下痢や嘔吐、出血、重度の熱傷などによって急激に体液が減少する際に起こります。
血圧低下やショック状態に陥る危険があり、適切な補水と電解質の補充が必要です。特に、大量の下痢や出血が続く場合には、医療機関での早急な対応が求められます。
低張性脱水
低張性脱水は、水分・ナトリウムをはじめとした電解質が減少したにもかかわらず、水分のみが補給され、血液中のナトリウム濃度が低下することで生じます。浸透圧によって、細胞外液から細胞内へ水分が移動し、血液を含む細胞外液量の減少を伴うことが特徴です。その結果、循環血液量の減少や循環不全を起こしやすく、特に血圧低下や意識障害を伴う場合には迅速な対応が求められます。
大量に汗をかいた際に、水分補給を水やお茶だけで行い、塩分を適切に補充しないと、この脱水が引き起こされます。また、頻回の嘔吐や下痢、副腎機能の低下、不適切な輸液管理なども誘因となるため、病態に応じた適切な補液が必要です。
脱水症は何日で治る?
脱水症状が改善するまでの期間は、その程度や原因によって異なります。一般的に、軽度の脱水であれば、水分を適切に補給し、安静にすることで数時間から1日程度で回復するといわれています。
しかし、強い倦怠感や頭痛、めまいを伴う場合は、回復により長い時間が必要でしょう。また、重度の脱水症になると体液バランスが大きく崩れており、医療機関での点滴治療が必要で、回復までに数日かかることもあります。
脱水の検査
脱水の診断は、問診や身体診察で得た情報をもとに行います。皮膚の乾燥や口の渇き、血圧の低下、脈拍の増加などの症状が見られる場合、脱水の可能性が高いと判断されます。また、既往歴や服用している薬の種類も、判断材料の1つです。
脱水の程度を詳しく調べるために、血液検査を行うこともあります。血液中のナトリウムやカリウムなどの電解質の濃度を測定することで、どのタイプの脱水が進行しているのかを確認できます。
脱水の対処法
脱水の症状が見られた場合、まずは適切な水分補給を行うことが重要です。水だけではなく、電解質を含む飲み物を摂取することで、体内の水分バランスを素早く整えることができます。
脱水によってめまいやふらつきが生じた場合は、すぐに安静にし、無理に動かないようにしましょう。症状が軽ければ、休息を取りながらゆっくりと水分補給を行うことで改善されます。しかし、症状が長引いたり、意識がもうろうとしたりする場合は、すぐに医療機関へ連絡し、適切な治療を受ける必要があります。
脱水のフィジカルアセスメント
脱水のフィジカルアセスメントでは、体重減少率や皮膚の冷感、口腔粘膜の乾燥度、呼吸や脈拍の変化などを指標として、脱水の重症度を評価します。
上述したように健康時からの体重減少率が3%未満であれば軽度、3~9%であれば中等度、10%以上になると重度です。
皮膚の冷感や毛細血管再充満時間の遅延は、中等度以上の脱水では四肢が冷たく感じられることが多いでしょう。重度では「かなり冷たい」と表現されるほど血流が低下し、末梢の血液供給が著しく減少していることがわかります。
呼吸や脈拍の変化も脱水の進行に伴い明確に現れます。軽度ではほぼ正常ですが、中等度になると呼吸がやや速くなり、脈拍も増加します。重度の脱水では呼吸が荒くなり、深く速い呼吸になることが多く、脈も速くなり触れにくくなるため、ショック状態へ進行する危険があります。
さらに、意識レベルの変化も見逃せないポイントです。軽度では「いつもと違う」と感じる程度の変化ですが、中等度では意識が混乱し、もうろうとすることがあります。重度になるとぐったりして反応が鈍くなり、昏睡状態に陥ることもあるため、直ちに医療機関での対応が必要です。
* * *
軽度の脱水であれば自宅での対策が可能ですが、倦怠感や意識の混濁などの重い症状が現れた場合は、速やかに医療機関を受診することが重要です。本記事で解説した内容を利用者さんとそのご家族のアセスメントに役立ててください。
| 編集・執筆:加藤 良大 監修:久手堅 司  せたがや内科・神経内科クリニック院長 医学博士。 「自律神経失調症外来」、「気象病・天気病外来」、「寒暖差疲労外来」等の特殊外来を行っている。これらの特殊外来は、メディアから注目されている。 著書に「気象病ハンドブック」誠文堂新光社。監修本に「毎日がラクになる!自律神経が整う本」宝島社等がある。 |







